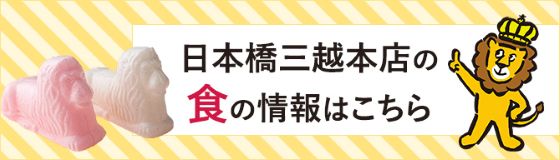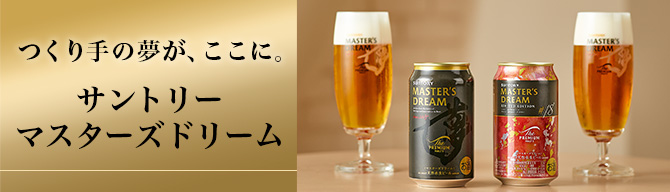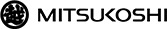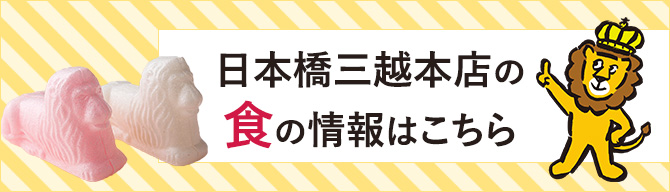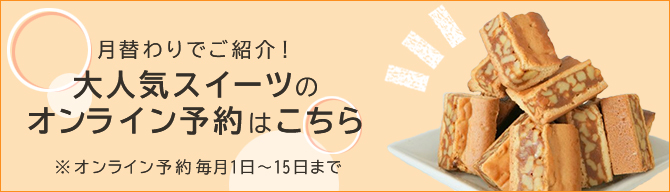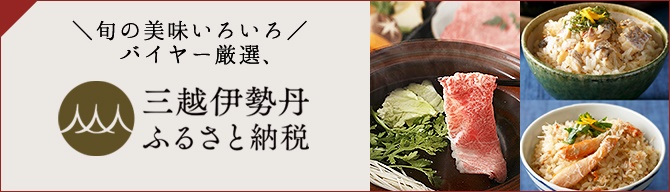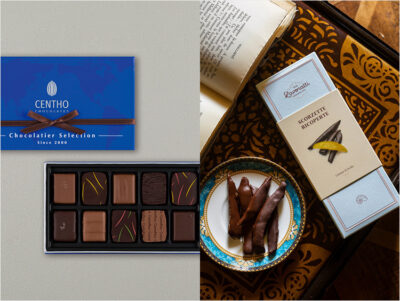2025.02.16
【台湾の味を追求】もっちりぷるぷる! 大根餅の人気レシピ。2つの粉使いにプロのコツあり

春巻きや焼売などと並び、中国・台湾料理の人気点心として日本でもおなじみの「大根餅」。香ばしく焼かれた大根餅のカリッ、もちっとした唯一無二の食感は、クセになる美味しさです。
その名の通り、主な材料は大根。日本で大根料理といえばブリ大根やおでんなど、煮もの一辺倒になりがちなので、目先の変わった大根餅がおうちでも作れたら嬉しいですよね!
そこで今回は、手に入りやすい材料で作れる本格的な大根餅のレシピを、本場・台湾に何度も足を運んで食べ歩き、作り比べているという、料理研究家の小島喜和さんに教わりました!
そもそも「大根餅」とは?
まずはレシピをチェックするまえに、大根餅とはどんな料理なのか解説します。
●大根餅はどこの国の食べもの?
大根餅は「蘿蔔糕(ローポーガオ)」と呼ばれ、中国の広東省、福建省から香港、台湾、シンガポールなどに広まりました。
●大根餅はどんなシチュエーションで食べられている?
香港や台湾では旧正月(春節)を祝う縁起のよい食べ物であり、香港では飲茶、台湾では朝食としても定番の国民食とも呼べます。
●大根餅の材料や作り方とは?
作り方は、米粉などの粉類と水を合わせた生地に、千切りの大根、そして干しえび、干し椎茸などの乾物や、腸詰(中国式ソーセージ)などの具材を混ぜ、型に流して蒸したあと、四角く切り分けてから表面を油で焼きます。
「大根餅」3つのポイント。味わい深く、ほどよいもちもち食感に仕上げる!
「大根餅はお店ごと、家庭ごとの味があります。台湾には何度か行っていて、いろいろなお店で食べ比べましたが、私にとってのナンバーワンはかつて自宅のご近所にあった、台湾人のご年配の夫婦が切り盛りされているお店の味。何とも味わい深く、もちもちし過ぎない食感がとても好きだったんです。今回はその味をイメージした、日本でも手に入りやすい食材で美味しく作れるレシピをご紹介します」
小島さん思い出の味とは期待が高まります! それではレシピのポイントをチェックしていきましょう。
【ポイント①】上新粉、うき粉の2つを使用。歯切れがよい、理想的なもっちり食感の大根餅になる!

左から、<富澤商店>うき粉(200g) 378円、新潟県産 上新粉 特(200g) 356円(ともに税込)
本格的な大根餅の材料には、日本のうるち米よりもデンプン質が少ないインディカ米を原料とした米粉(在来米粉など)が使われています。
「インディカ米の米粉を使うと粘りが少ない軽い仕上がりになりますが、日本米は風味にクセがなく美味しいので、日本米を原料とする『上新粉』を使った方が私は好みです。ただ、これだけだと食感がもちもちし過ぎて重いので、『うき粉』を混ぜてバランスをとります」
うき粉(浮粉、浮き粉)とは、小麦粉から粘りや弾力を生む「グルテン」を取り除き、残ったデンプンを精製した粉のこと。加熱すると片栗粉のように半透明でプルンとした食感になり、生地に混ぜるとふんわりと仕上がるので、点心の蒸し餃子やごま団子の皮、たこ焼きや明石焼きの生地のほか、餅とり粉(餅を成形するときにまぶす粉)としても使われます。
「うき粉を混ぜることでプルンとした食感が加わって歯切れがよくなり、軽い味わいに仕上がります」
うき粉が手に入らない場合、片栗粉、コーンスターチで代用することも可能です。ただし、注意点があるので、こちらを確認してください。
※取扱い:日本橋三越本店 新館地下2階 富澤商店
【ポイント②】千切りにした大根はゆでてから水気を絞る。適度に水分が抜け、生地の状態が安定する!
大根は千切りにして水からゆでて、少しコシを残した状態で引き上げ、適度に水気を絞って生地に混ぜます。
「大根餅の作り方にはいろいろあり、塩もみした大根を混ぜたり、大根を生のまま炒めて混ぜたりする方法もありますが、試作を重ねた結果、この方法にたどり着きました。大根は水分量に個体差がありますが、この方法で作るとでき上がりの食感が安定します。ただし、レシピの分量以上に大根を増やすと生地がやわらかく、ベタっとするので注意してください」
【ポイント③】大根餅は強火でしっかりと蒸す。粉くささが飛んで美味しくなる!
「大根餅は粉類を多く使うので、どうしても『粉くささ』が出やすいのですが、強火でしっかり蒸し、粉に火を通しきれば匂いは飛びます。また、干しえび、長ねぎを香りが出るまで油で炒めるのも、粉くささをやわらげる大事なポイントです」
台湾の味を再現! 「大根餅」の本格レシピ

<材料>(約14×11×高さ4.5㎝、容量約800mlの流し缶1台分)
- 大根(皮をむく)…正味200g
- 干しえび…15g
- 長ねぎ…1/2本(60g)
- 【A】
・上新粉…150g
・うき粉…30g ※片栗粉、またはコーンスターチで代用可
・塩…小さじ1
・砂糖…小さじ1と1/2 ※写真は洗双糖(せんそうとう)。上白糖など好みのものでOK
・水…150ml - サラダ油…適量
- 【つけだれ】
・酢、しょうゆ…各適量
【注意点】うき粉を片栗粉やコーンスターチで代用する場合
うき粉が手に入らない場合、片栗粉、またはコーンスターチで代用することも可能です。ただし、次第にかたくなり食感が損なわれていくので、早めに食べることをおすすめします。冷凍保存はおすすめしません。
●今回、使用した流し缶


今回型に使用した流し缶。ステンレス製なので熱に強い。二重構造になっていて、取っ手付きの底板を引き上げれば中身を崩すことなく取り出せる。
型は耐熱のバットや保存容器、パウンド型などで代用可。その場合、ラップを敷いてから生地を流すと取り出しやすい。
<作り方>
1. 干しえびは水で10分ほどもどし、みじん切りにする。長ねぎはみじん切りにする

小さな容器に干しえびを入れ、【A】の水から大さじ2を取り分けて加える。10分ほどもどしたら(写真)、もどし汁は【A】の水と合わせ、干しえびはみじん切りにする。長ねぎはみじん切りにする。
「干しえびは写真のように、軽くもどればOKです」
2. 大根は千切りにして水からゆでる。ザルに上げて湯をきり、冷めたら水気を軽く絞る

大根はうすい輪切りにしてから千切りにする。
「大根餅にすると大根は生地になじんでしまうので、太さによる食感の違いは不思議と感じられません。今回は千切りにしましたが、もっと太く切っても構いません」

鍋に大根とかぶる程度の水、ひとつまみの塩(ともに分量外)を入れ強火にかける(写真)。煮立ったらフツフツと沸くくらいの火加減に弱めてゆでる。
「塩を加えると大根から水分が出やすくなります」

大根に透明感が出て、まだコシが少し残っている状態になったら(写真)、ザルに上げて湯をきる。粗熱がとれるまでそのまま冷ます。
「今回は沸騰してから10分ほどゆでましたが、使用する大根によってゆでる時間は変わります」

大根の水気を軽く絞る。
「ギュッと力を入れる必要はありません。やさしく握り、写真のようにひとまとめになればOKです」
3. 【A】を混ぜ合わせ、生地を作る

ボウルに【A】の粉類を入れて泡立て器で混ぜ合わせ、干しえびのもどし汁が入った【A】の水を加える(写真)。

泡立て器で全体を混ぜ、粉に水分を吸わせる。
「混ぜにくければ、ゴムベラで混ぜても構いません」
4. 干しえび、長ねぎ、2の大根を炒め、水250mlを加えて煮る

フライパンにサラダ油大さじ1弱を入れ、中火にかける。1の干しえび、長ねぎを加えて耐熱のゴムベラ(または木べら)で炒め(写真)、香りが立ってきたら2の水気を絞った大根を加えて炒め合わせる。

全体が混ざったら水250ml(分量外)を加える。

沸騰したら、すぐに火を止める。
5. 3の生地に4を加えて混ぜ合わせる


3の生地に4を加え(上写真)、ゴムベラ(または木べら)で粉のかたまりがなくなるまでよく混ぜ合わせる。
「使用する上新粉によって、混ぜ終わりの生地のゆるさが多少異なります。今回はゆるめになりましたが、かためでも、ゆるめでも、仕上がりの状態は変わりません」
6. 流し缶に生地を流し入れ、蒸し器に入れる。強火で35分ほど蒸し、冷蔵庫で冷やす

流し缶に5を流し入れ、蒸気の上がった蒸し器に入れる。全体に火が通るまで、強火で35~40分蒸す。
「途中でお湯がなくならないよう、途中で様子を見て、適宜足しましょう」

蒸し上がったら(写真)、取り出してそのまま粗熱をとり、ラップをかけて冷蔵庫に入れて冷やす。
「温かいと包丁に生地がベタベタとくっついて切りにくいです。きれいに切るためには、冷蔵庫でしっかり冷やしてください」
7. 2㎝幅に切り分け、たっぷりの油でこんがりと焼く

大根餅を型から取り出し、サラダ油(分量外)を塗った包丁で約2㎝幅に切り分ける。
「包丁に油を塗っておくと、生地がくっつきにくく切りやすいです」

フライパンにサラダ油を多めに入れ、中火で熱し、大根餅を並べ入れる。両面をこんがりと焼いてから側面も同様に焼き、器に盛る。好みで、酢じょうゆのつけだれをつけていただく。
「フッ素樹脂加工のフライパンを使用する場合でも、油をたっぷりと使って揚げ焼きするように焼くと、縁がカリッと香ばしくなって美味しいです」
●大根餅の保存期間
切り分ける前の状態でラップに包むか、切り分けてからラップに包み、冷蔵庫で4日ほど。切り分けてラップに包み、保存袋に入れて密閉し、冷凍庫で1か月ほど保存が可能。
ただし、うき粉が手に入らず、片栗粉やコーンスターチで代用した場合は、味や食感が落ちていくので早めに食べること。冷凍保存もおすすめしません。
【実食】大根餅。大根のみずみずしさと、もっちりぷるぷる食感に箸が止まらない!


大ぶりに切った大根餅を、お箸で切り分けていただきます。縁はカリッと香ばしく、中はもっちりとした弾力がありつつぷるぷるとした食感で、大根のみずみずしさ満点! 口の中で大根がとろけるように消えていくのと同時に、干しえびと長ねぎの香ばしさとうま味がじんわりと広がり、ついもう一口と手が伸びます。
淡白な味わいの大根は、主役というよりも具材を引き立てる名脇役。結構な食べごたえがあるはずですが、いくらでも食べられるほど軽やかな味わいで、食感のコントラストが楽しく、すっかり虜になってしまいました。
おかずとしても、おつまみとしても間違いなしの美味しさで、しかも保存が効くので長く楽しめるのも嬉しいポイントです。みなさんも、大根の美味しい季節にぜひ作ってみてください!
レシピ/小島喜和さん

料理・菓子研究家。季節の手仕事を得意とし、梅仕事や味噌作りなど、各種ワークショップを開催。また、ニューヨーク、パリの製菓学校で製菓、製パンを学び、ディプロマを取得した経験を活かし、料理教室、お菓子教室を主催している。
高知県出身で、地元の郷土料理や食材を広める活動はライフワーク。『心ふるえる土佐の味』(高知新聞社)、『みそさえあれば。』(日東書院本社)、『四季を愉しむ手しごと』(河出書房新社)など著書多数。
商品の取扱いについて
記事で紹介している商品は、日本橋三越本店 新館地下2階 富澤商店にてお取扱いがございます。
※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。
※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。
Ranking
人気記事ランキング