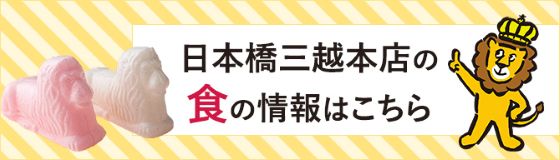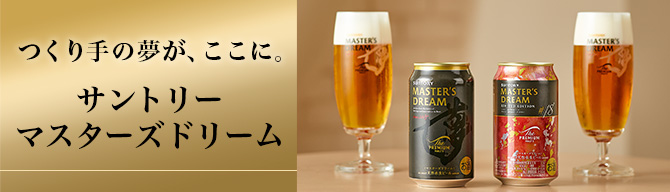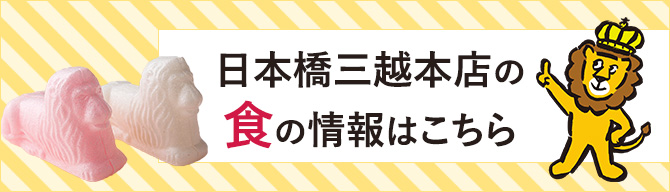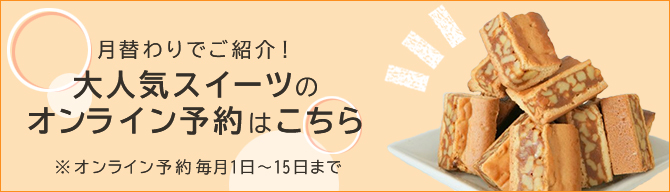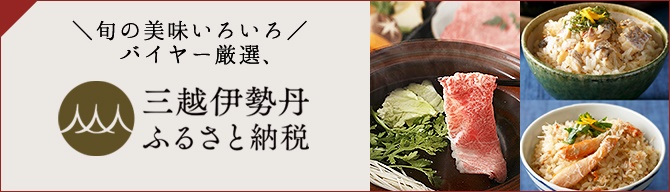2025.10.16
【簡単】冷めてもしっとり! 鶏そぼろレシピ。炒り卵との三色丼や弁当にも人気です

新米の季節になると欲しくなるのが、ご飯のお供。そのなかでも「鶏そぼろ」は幅広い世代に人気で、炒り卵と緑野菜とともにカラフルに盛り付けた三色丼やお弁当は定番ですよね。少ない材料で作り置きがきくので、常備菜としても作っておきたい肉おかずです。
でも、いざ作ろうとすると、炒めて作るのか煮て作るのか、ひき肉はもも肉とむね肉(胸肉)のどちらを使うのか、豚肉や牛肉で作ってもいいのかなど、世の中に出回っているレシピはさまざま…。
そこで今回は料理研究家の橋本加名子さんに、冷めてもしっとりやわらかい「鶏そぼろ」の作り方を教えてもらいました。
「鶏そぼろは、鶏肉の部位の選び方や火の入れ方で仕上がりが大きく変わります。ほろほろと口溶けがよく、冷めてもしっとりふっくら、うま味とコクたっぷりの鶏そぼろの作り方をご紹介します。鶏そぼろの三色丼に合う『炒り卵』レシピもぜひ一緒に作ってみてください」
さっそく、気になるレシピのポイントをチェックしていきましょう!
目次
ふんわりしっとり、うま味とコクが豊か!「鶏そぼろ」3つのポイント
「ひき肉を使ったそぼろには、牛肉、豚肉、鶏肉がありますが、牛と豚はクセが強く、冷めると脂が白くかたまりやすいです。常備菜(作り置き)にしたい場合は、鶏肉で作るのがおすすめです。
なお、鶏もも肉と鶏むね肉(胸肉)で作ったときの違いについては【ポイント③】で解説します。まずはレシピ通りに作ってみてください」
【ポイント①】火にかける前の煮汁にひき肉を入れ、完全にほぐしてから火にかける。ダマにならず、ふんわり、しっとり仕上がる!

鶏そぼろのレシピを調べると、鶏ひき肉を炒めてから調味料を加える作り方と、調味料で煮る作り方の2つに分かれます。さらに煮る場合は、火にかける前の常温の煮汁にひき肉を加えるやり方と、温めた煮汁にひき肉を加えるやり方に分かれ、一体どれが正しいのでしょう?
「火にかける前の煮汁にひき肉を入れ、煮る作り方がおすすめです。炒めて作るとひき肉がダマになりやすく、ふっくらした味にならず冷めるとかたくなりやすいです。温めた煮汁にひき肉を加えて煮る方法は、ダマになりやすいのでおすすめしません。
火にかける前の煮汁にひき肉を入れ、完全にほぐしてから火にかけ、肉に火が通るまでは混ぜ続け、火が通ったらときどき混ぜるとパラパラに仕上がります。さらに、熱がひき肉にゆっくり伝わるので、しっとり仕上がります」
【ポイント②】多めの煮汁でゆっくり煮詰める。煮汁に鶏のうま味が引き出され、味に一体感が生まれる!
ひき肉を煮るときは、煮汁の量も大事。ある程度の量の煮汁でゆっくり煮詰めると、鶏のうま味が煮汁にいったん出て調味料と混ざり合い、ひき肉に戻るので味が一体化します。水分を飛ばすとパサつくのでは? と心配になるかもしれませんが、脂も煮汁に溶け出て、全体にまわるのでしっとり仕上がります。
【ポイント③】鶏のひき肉は「もも肉」と「むね肉(胸肉)」を2:1の割合でブレンド。いいとこ取りで理想的な仕上がりに!

鶏のひき肉には、部位の違う「もも肉」と「むね肉(胸肉)」の2種類があります。もも肉は脂が多く肉質がやわらか。一方、むね肉は脂が少なく肉質が締まっています。色味はもも肉の方が、ピンク色が濃いのが特徴。
「鶏もも肉だけだとやや脂がしつこくクセがあり、鶏むね肉だけだと口当たりが悪い印象です。そこでそれぞれの特徴を生かし、もも肉とむね肉を2:1の割合で作るのがおすすめ。しっとりふっくらとして、適度に脂のコクがあり、うま味たっぷりの理想的な味わいに仕上がります」
この検証のために、鶏もも肉と鶏むね肉でそれぞれ鶏そぼろを作り、食感・味わいについて温かい状態と冷たい状態で比較をしてみました。以下にご紹介しますので、気になる方は参考にしてください。
●「鶏もも肉」で作ったそぼろ。食感・味わいの比較

鶏もものひき肉は脂が多いので、しっとり、ふっくらとやわらかく、噛むとすぐに消えます。味わいはコクが強くこってりして、鶏肉特有の匂いを若干感じるので人によってはクドく感じるかもしれません。
冷たい状態だと底にたまった肉汁にコラーゲンが多く含まれているので、煮こごり状態にかたまります。白い脂は多少浮きますが、白くかたまるほどではないです。
●「鶏むね肉」で作ったそぼろ。食感・味わいの比較

一方、鶏むねのひき肉は脂が少ないので、しっかりとした食感。少し口に残る感じがするので、人によってはパサついたように感じるかもしれません。さっぱりと淡泊な味わいですが、噛むほどにうま味が感じられます。
冷たい状態だでも底にたまった肉汁は、もも肉ほどかたまりません。白い脂はほぼ浮いていません。
確かに。鶏もも肉とむね肉で作ったときの比較を見ると、ブレンドする意味が理解できました! さあ、作り方のポイントを押さえたところで、いよいよレシピをご紹介します。
基本の「鶏そぼろ」簡単レシピ。2種類のひき肉使いに注目!

<材料>(作りやすい分量)
- 鶏ももひき肉…200g
- 鶏むねひき肉…100g
- 【煮汁】
・水…100ml
・しょうゆ…大さじ2と1/2 ※保存性を高めたい場合、増やすとよい
・日本酒…大さじ3
・みりん…大さじ2
・砂糖(きび砂糖など)…大さじ2
・しょうがの絞り汁…小さじ1
「しょうゆの分量はお好みで増やしても構いません。お弁当に入れるなら保存性を考慮して濃い味にするのがおすすめです。最大でもしょうゆ大さじ3と1/2までにするといいでしょう。鶏そぼろだけ食べるとしょっぱく感じるくらいの味加減です。煮汁には鶏肉のクセがやわらぐよう、香りづけにしょうがの絞り汁を加えます」
<作り方>
1. 鍋に煮汁の材料と鶏ひき肉を入れ、菜箸を4本束ね、肉が完全にほぐれるまで混ぜ合わせる


鍋に【煮汁】の材料とひき肉を入れ、4本束ねた菜箸で混ぜ合わせ(上写真)、完全にほぐす(下写真)。
「菜箸を束ねてひき肉をほぐし、加熱し終わるまで混ぜ続けます。泡立て器を使うと楽ですが、泡立て器にひき肉がくっついて洗うのが面倒なので、私は菜箸を使っています。
鍋は行平鍋のように、底の角が丸まっていると均一に混ざりやすいのでおすすすめ。フライパンだと煮汁が飛びにくく、粒が若干大きく仕上がります」
2. 中火にかけ、鶏ひき肉に火が入るまで菜箸で混ぜ続ける

鍋を中火にかけ、菜箸でグルグルと混ぜ続ける。
「ひき肉の色が変わって火が入るまで、ほぐすように混ぜ続けてください」

「ひき肉に火が入ると、もうダマにはならないのでときどき混ぜる程度でOKです。煮汁が増えてシャバシャバとした状態になり、鍋の縁にアクが多少浮きますが(写真)、混ぜ続けるうちに消えるので私はそのままにしています。気になるようなら取り除いてもよいでしょう」
3. ときどき混ぜ、鍋底に箸の跡が残る程度まで煮詰めたら完成

ときどき混ぜながら、煮汁を煮詰める。

煮汁がほぼなくなり、箸で鍋底をなぞると跡が残るようになったら完成(写真)。火から下ろす。
「火にかけてから、だいたい12分くらいで完成です。脂はたいして浮きませんが、苦手ならキッチンペーパーで吸い取ってください」

鶏そぼろのでき上がり

白いご飯に、鶏そぼろ、炒り卵、ゆでてしょうゆと白ごま各適量をまぶしたさやいんげんと一緒に盛り付ければ、三色そぼろ丼のでき上がり。
●鶏そぼろの保存方法とおすすめの食べ方。たっぷり作ってアレンジを楽しもう!

【保存方法】冷蔵保存する場合は粗熱がとれたら密閉容器に入れ、冷蔵庫で3~4日程度。冷凍保存する場合は粗熱が取れてから小分けにしてラップに包み、保存用密閉袋に入れ(写真)、冷凍庫で1カ月程度保存が可能。
【おすすめの食べ方】鶏そぼろは玉子焼きに混ぜたり、大根やかぼちゃ、里芋などと一緒に煮たり、豆腐や焼いた厚揚げ豆腐に細ねぎをのせてラー油をかけたり、ゆでた素麺や中華麺に絡めて「和え麺」にしたり、炒飯にしたりと、いろいろなアレンジができるので、たっぷり作って保存するのがおすすめです。
お弁当にする場合は、一度電子レンジなどでしっかり温めなおし、冷ましてから持っていってください。
鶏そぼろは三色丼にして実食! しっとり、ふわふわ、箸が止まらない美味しさ

まずは鶏そぼろだけで一口。濃厚な鶏のうま味と、ほどよい脂のコクがジュワッと広がります。鶏特有の臭みもなく、しっとり、ふわふわとしていますが、鶏らしい噛みごたえも感じられます。
お次は、炒り卵、ゆでてしょうゆと白ごまをまぶしたさやいんげんとの三色丼。食卓が一気に華やいで気分が上がります! しっかりとした味わいの鶏そぼろと、ごはんの組合せは絶妙なバランス。ほんのり甘じょっぱい炒り卵のやさしさと、いんげんのみずみずしさが後を引き、食べる手が止まりません…。これは常備菜として、たっぷり作らなければ。
身近な材料で簡単に作れるので、みなさんもぜひお試しください。
【鶏そぼろ丼に相性抜群】「炒り卵」レシピ。冷めてもかたくならない!

しっかりとした味わいの鶏そぼろに合うよう、砂糖と塩で、うっすら甘じょっぱく仕上げた炒り卵。日本酒が入るとうま味がアップし、さらに水を加えると冷めてもしっとりした状態に。鶏そぼろと同様、菜箸を束ねて混ぜながら作ります。

<材料>(3~4人分)
- 卵…5個
- 水…50ml
- 日本酒…大さじ2
- 砂糖(きび砂糖など)…大さじ1
- 塩…小さじ1/4
<作り方>
1. 鍋(行平鍋など、底の角が丸いもの)に卵を割りほぐし、カラザ(白身のかたまり)を取り除く。残りの材料を全て加え、よく混ぜ合わせる。

2. 鍋を中火にかけ、4本束ねた菜箸でグルグルと絶えず混ぜ続ける。

3. 卵に火が入りかたまってきたら、細かくほぐすように菜箸で混ぜ続ける。

4. 卵に完全に火が入り、ポロポロとした状態になったら火から下ろす。

レシピ/橋本加名子さん

料理研究家、栄養士、フードコーディネーター、国際薬膳調理師、防災士。タイ料理、ヴィーガンタイ料理、和食、発酵の料理教室「おいしいスプーン」主宰。企業で働きながら子育てをした経験を活かし、「体にやさしくて、作りやすい家庭料理」を提案し続けている。飲食店のプロデュースやフードコーディネートにも携わる他、雑誌、書籍、ウェブサイト等で活躍。『ホットクックお助けレシピ』シリーズ(河出書房新社)、『アイラップで簡単レシピ』(Gakken)、『麹豆乳クリームレシピ』(ブティック社)など著書多数。
※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。
※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。
Ranking
人気記事ランキング