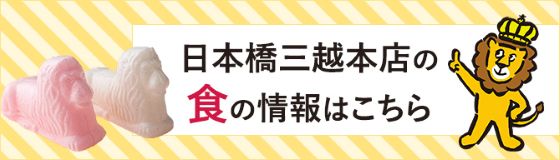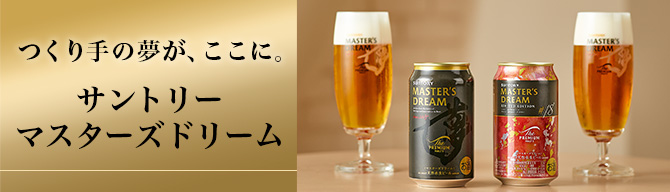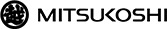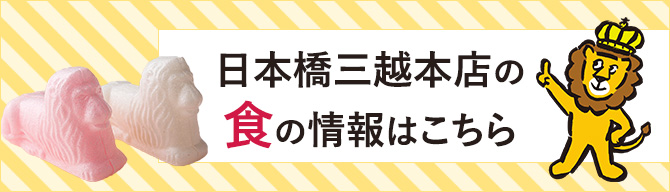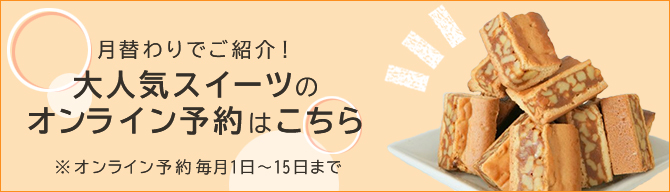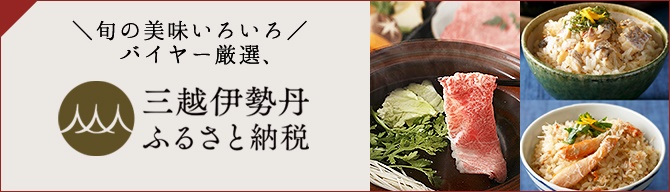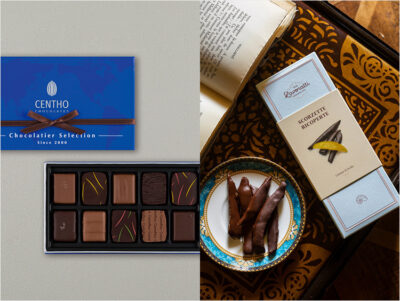2025.04.10
春の香り!「よもぎ餅(草餅)」の作り方。乾燥よもぎ、米の粉レシピもご紹介

春の野原ではやわらかな緑をした「よもぎ」の若芽があちらこちらに。毎年この時季を心待ちにし、摘み取って「よもぎ餅(草餅、草もち、草だんご)」を作る方も多いのでは? 市販の「乾燥のよもぎ」を使えばいつでも作れますが、フレッシュな生よもぎを使えるのは春から初夏だけの醍醐味です。
「私は春になると、高知県・土佐清水市の実家の庭で採れるよもぎで、よもぎ餅作りを楽しんでいます。餅生地は米の粉(上新粉、もち粉、白玉粉)を使って作るレシピをよく見かけますが、私のおすすめはもち米で作るもの。つきたてのお餅から漂うよもぎの香りは格別ですよ」
そう話すのは、日本の伝統食や季節の手仕事を得意とする料理研究家の小島喜和さん。私は上新粉を使ったよもぎ餅しか作ったことがないので、おすすめのもち米で作るよもぎ餅のレシピ、ぜひ教わりたいです!
「よもぎの下処理の方法から解説します。お餅はつけないけどよもぎ餅を作ってみたい、生のよもぎが手に入らないけど作ってみたい、という方のために、米の粉(上新粉、もち粉)を使ったレシピ、乾燥よもぎを使ったレシピも記事の最後でご紹介します」
よもぎ餅レシピ完全版ですね! まずはレシピをチェックする前に、よもぎ餅とはどんな食べ物なのかおさらいしていきましょう。
目次
春の伝統和菓子「よもぎ餅(草餅)」とは?
●草餅とは、江戸時代から「よもぎ」が主流。さらに昔は「御形(ごぎょう)」を使っていた
現在、一般的に草餅といえば、よもぎ餅のことを指しますが、かつては違う植物が使われていました。
春の季語としても知られる草餅の歴史は古く、平安時代に中国から伝えられた行事食が起源とされています。草の香りや薬効が邪気を払うという考えから、桃の節句の起源となった3月3日の「上巳節」に、身の穢れを清めるために食されていたのです。
当時、草餅には母子草(春の七草でもある「御形」)が使われていたため、「母子餅」という名称が一般的でしたが、母子をつくので縁起が悪いと考えられるようになり、江戸時代にはよもぎを使用した草餅が主流になりました。
●よもぎ餅に使う「よもぎ」とはどんな植物?
よもぎ餅に使われるよもぎは、日本各地の野山や空き地に自生するキク科の多年草。繁殖力が非常に高く、春に芽を出し、茎を派生させながら秋には背丈が60~120㎝に成長したのち、茎と葉は枯れますが、根は休眠状態で冬を越します。
漢方の生薬としても使われるほどの薬効があり、食べる、飲む、香りをかぐ、お灸のもぐさや入浴剤にするなど、古くから万能薬とされてきました。
●よもぎ餅には春は「生」、それ以外の季節は「乾燥」を使用


よもぎは成長するほどにアクが強く、筋っぽくなるので、よもぎ餅には3月下旬~5月上旬の若い芽(葉)を摘み取って使いましょう。

<富澤商店>国産 よもぎパウダー(40g) 604円(税込)
収穫時季に採れたよもぎを乾燥させたものや、乾燥させてからパウダー状にしたものを使えば、一年中よもぎ餅を楽しむことが可能です。
※取扱い:日本橋三越本店 新館地下2階 富澤商店
●よもぎ餅(草餅)の食べ方は?
あんこや、砂糖を加えたきな粉と一緒にいただくのが一般的。ぜんざい(お汁粉)に加えるのもおすすめです。
【基本レシピ】生よもぎ×もち米を使った「よもぎ餅(草餅)」の作り方

「餅生地には、ふんわりと伸びのよい食感に仕上がるもち米を使います。米の粉を使うと柏餅のように歯切れのよい食感に仕上がり、それはそれで美味しいのですが、もち米の方が香りにクセがなく、よもぎ自体の香りを素直に楽しめます。
また、今回使用した生のよもぎは、私が育った土佐の実家の庭で採れたものです。ほんの出はじめのアクが少なくやわらかい状態だったので、たっぷりと混ぜ込みました。よもぎによって風味や色味も異なるので、お好みの量をお使いください」

<材料>(作りやすい分量)
- よもぎ餅
・よもぎ(生)…適量(今回は185gのうち、可食部約80gを使用)
・重曹…小さじ1~2 ※湯1ℓに対して小さじ1の割合で加える
・もち米…2合
・片栗粉(または餅とり粉、きな粉)…適量 ※餅を成形するときに使用 - 好みで、あんこ(粒あん、またはこし餡)…適量(餅1個に対し20~30g)
- 好みで、きな粉、砂糖…各適量

<富澤商店>新潟県産 こがねもち(もち精米)(1kg)1,436円(税込)
※取扱い:日本橋三越本店 新館地下2階 富澤商店
▼関連記事もチェック!
小島喜和さんが教える、粒あんのレシピはこちら>>
<下準備>
・もち米を研ぎ、蒸し器で蒸す場合は6時間以上浸水し、使用する15分前にザルに上げて水気をきっておく。炊飯器で炊く場合は1時間浸水し、使用する直前にザルに上げて水気をきる
▼関連記事をチェック!
炊飯器を使った、もち米の炊き方はこちらを参照>>
・あんこが手で丸められないほどやわらかい場合は、鍋で加熱して水分を飛ばしておく
▼関連記事をチェック!
あんこが手にベタベタとくっついてしまう場合はこちらを参照>>
<作り方>
1. よもぎの可食部(食べられる部分)を選り分け、よく洗う

よもぎの根本から葉先に向かって手でしごいたときに、ゴワゴワとした感触の葉があれば摘み取って除く。
「ゴワゴワとした葉は成長が進んでかたくなっていたり、枯れていたりします。ゆでても筋っぽさが残るので取り除いておきましょう」


次に茎を広げ、一番上にくる茎(上写真、赤色部分)を根元から摘み取る(下写真)。
「この部分はもっとも若い新芽になります。ほかの葉や茎に比べて色が明るく、やわらかいので茎ごと使えます」

残りの葉を摘み取る。すべて選り分けたら水を入れたボウルの中でよく洗い、汚れを落とし、ザルに上げて水気をきっておく。
「写真の赤色部分が可食部になります。今回は185gのよもぎから可食部が80gほど取れました」
2. よもぎをゆでる。鍋に湯を沸かし、重曹を加えてよもぎをゆで、水にとってアクを抜く

大きめの鍋に水1~2ℓを注いで強火にかける。沸いたら重曹(水1ℓに対して小さじ1)を入れる。
「重曹を入れるとよもぎのアクが抜け、繊維がやわらかくなり、色よく仕上がります」

1のよもぎを加えてゆでる。

煮えてきたら茎を親指と人差し指でつまみ、火の通り具合を確認し、すぐに繊維がつぶれない程度のやわらかさになっていたら火を止める。
「アクの強いよもぎの場合、ゆで汁が写真よりも黒ずみます。ゆですぎると香りが飛んでしまうので気をつけましょう」

ザルに上げて水を入れたボウルによもぎを入れ、煮汁の色が抜けるまで水を2~3回替える。さらに1~20分ほど水にさらし、アクを抜く。
「よもぎによってアクの量が違うので、水にさらす時間が変わります。今回はかなり若い芽でアクが少ないので1分程度浸水しましたが、途中で食べて見極めるのがおすすめです」
3. ゆでたよもぎをフードプロセッサーまたは包丁で刻み、さらにすり鉢でペースト状にする

2をザルに上げ、水気を軽く絞って包丁でざく切りにする。フードプロセッサーに入れ、細かくなるまで攪拌する。フードプロセッサーがない場合は、包丁で細かく刻む。
「繊維質が多いよもぎは、フードプロセッサーを使うと簡単に細かくできます。適度に水分がないと空回りしてしまうので、軽く絞る程度にしましょう」

よもぎをすり鉢に移し、すりこ木であたってペースト状にする。

写真のような太い筋があれば取り除く。
「太い筋は食感が悪いので、この段階で取り除いておきます。よもぎを加える量が多くなると水分量も増えて餅がやわらかくなるので、お好みで厚手のキッチンペーパーやガーゼに包んで、適度に水気をきっておくとよいでしょう」
●ゆでたよもぎを保存する方法
よもぎはゆでた状態で保存が可能です。よもぎをゆでたあと、包丁でざく切りにした段階か、ペースト状にした段階でラップに包み(量が多ければ1回分ずつ小分けする)、保存用密閉袋に入れてから冷蔵庫または冷凍庫で保存しましょう。冷蔵の場合は3日ほど、冷凍の場合は1か月ほど保存が可能(使用する際は自然解凍)。
4. もち米を蒸し器で蒸す。または炊飯器で炊く

蒸し器(今回はステンレス製を使用)でもち米を蒸す。蒸し器の下段に水をたっぷり入れておく。上段の内側に濡らしてかたく絞った蒸し布を敷き、もち米を入れて広げ、全体がでこぼことした形になるよう指で蒸し布の底を露出させる(写真)。蒸し布の端を中心に寄せてもち米を覆うようにして包み、ふたをして強火にかける。
「もち米を平らにするのではなく、あえてでこぼことした形にして蒸気の抜け道を作ります。こうするともち米全体に蒸気が伝わり、蒸しムラが防げます」
▼関連記事をチェック!
炊飯器を使ったもち米の炊き方はこちら>>

沸騰してから15分ほど加熱したらいったん火を止め、ふたを取って蒸し布を広げる。手で全体に水100ml(分量外)をかける(写真)。

もち米の上下を返して(写真)蒸し布で覆い、ふたをして強火にかける。再度沸騰したら5分加熱する。
5. もち米とよもぎのペーストを合わせ、餅つき機でつく

4のもち米を熱いうちに餅つき機(または餅つき機能付きのホームベーカリーや、パン用ニーダー)に移し、3のよもぎのペーストを加え、餅をつく。
「回りにくい場合は、ときどき水で濡らしたゴムベラを底から差し込み、返してください」
▼関連記事をチェック!
餅つき機を使わず、つきたて餅を手作りするレシピはこちら>>

もち米とよもぎが混ざり合って餅状になったら、餅のつき終わり。


片栗粉(または餅とり粉)を敷いたバットに餅を移し、水(分量外)をつけた手でのばし広げる(上写真)。粉が内側に入らないようにして、半分に折りたたむ(下写真)。これでよもぎ餅の完成。
「餅がバットにくっつかないよう、片栗粉を敷いておきます。餅の内側に粉が入るとかたくなるので、表面にだけつくように気をつけましょう。私の実家では、片栗粉ではなくきな粉を敷いていました。きな粉がお好きならこのやり方がおすすめです」
平らにのばした状態で2日ほどおき、よもぎ入りのし餅(切り餅)にしてもよい。
▼関連記事をチェック!
つきたて餅で「のし餅(切り餅)」をつくるレシピはこちら>>
【初心者向き】よもぎ餅の食べ方
●よもぎ餅を丸めてきな粉をまぶす。好みであんこを添えても

よもぎ餅を食べやすいサイズにちぎってから丸めて(ちぎったままでもOK)、好みの量の砂糖を加えたきな粉をまぶし、あんこを添えていただく。
なお、必ずしも餅が熱いうちに作業する必要はないので、扱いづらい場合は、1時間ほど冷ましてから作業するとよい。
【中級者向き】よもぎ餅の食べ方
●よもぎ餅にあんこを包む

よもぎ餅であんこを包む場合は、餅1個につきあんこを20~30gに丸めておく。

よもぎ餅を1個45~50gになるよう、ちぎって計量する。必ずしも餅が熱いうちに作業する必要はないので、扱いづらい場合は、1時間ほどおいて冷ましてから作業をするとよい。
「よもぎ餅をちぎるときは、手に餅がくっつかないように手粉をつけましょう」

直径約10㎝の円形にのばす。
「外側をうすめにのばすと、合わせ目が厚ぼったくならず、形よく仕上がります」

中央にあんこをのせる。

餅であんこを包み、あんこを中に押し込みながら餅の縁を中央に寄せ、口をしっかり閉じる。


閉じ口を下にして、掌で包むように転がし、形を丸く整える。
【実食】よもぎ餅。春をそのままいただくような、目の覚める香り高い味わい!

今回使用したよもぎはとても若いことあり、毎年作っている小島さんも驚くほどの色鮮やかさ! 口に含むと鮮烈な草の香りがふわっと広がって、全身で「春」を感じられます。
これまで上新粉などの米の粉を使ったよもぎ餅は作ったことがあったのですが、もち米を使って作るのは初めて。一口いただいて、小島さんがおすすめする理由がすぐに分かりました。繊細なよもぎの香りを、つきたてのお餅が引き立ててこれ以上ない美味しさです!
「餅米の生地は時間が経つと早くかたくなるけど、生よもぎを入れると不思議とかたくならないんです」との言葉通り、やわらかさも長続き。この時季だけの雅な味を、ぜひお試しください。
ほかにもある! よもぎ餅の作り方3通り
「生よもぎ×米の粉(上新粉、もち粉)」、「乾燥よもぎ×米の粉(上新粉、もち粉)」、「乾燥よもぎ×もち米」を使った、3通りの作り方を紹介します。それぞれに食感や風味が異なり、食べ比べてみるのも楽しいものです。
【よもぎ餅レシピ①】生よもぎ×米の粉(上新粉、もち粉)

撮影:WEB FOODIE編集部
餅つき機がなくても、生よもぎを使った餅が作れるレシピ。生よもぎのやさしい風味と、コシのある餅生地の相性は、もち米生地とはまた違った良さがあります。
<材料>(作りやすい分量)
- よもぎ餅
・よもぎ(生)…適量
・重曹…小さじ1~2 ※湯1ℓに対して小さじ1の割合で加える
・上新粉…200g
・もち粉…30g
・砂糖…好みで大さじ1~2 ※入れると生地がやわらかくなる
・ぬるま湯(約50℃)…170~200ml
・片栗粉…(または餅とり粉、きな粉)…適量 ※餅を形成するときに使用 - あんこ(粒あんまたはこし餡)…好みで適量(餅1個に対し20~30g)
- きな粉、砂糖…好みで各適量
<作り方>
1.「基本のよもぎ餅の作り方」の作り方1~3と同様にする。
2. ボウルに上新粉、もち粉、好みで砂糖を入れて混ぜ合わせる。50℃のぬるま湯を少し残して加え、ゴムベラでざっと混ぜる。
3. 1のよもぎを加えてゴムベラで混ぜ、途中から手でもみ込む。耳たぶ程度のやわらかさになるよう、かたければ残りの水を加減しながら加え、ひとまとめにする。
4. 8等分して小判型に丸め、真ん中をへこませる(下写真)。蒸気の上がった蒸し器で15~20分蒸す。

5. すり鉢、またはボウルにうつし、すりこぎでつく(下写真)。


6. ひとまとめにして完成。食べる際は、手水をつけてちぎったり丸めたりして、お好みであんこやきな粉とともにいただく。
【よもぎ餅レシピ②】乾燥よもぎ×米の粉(上新粉、もち粉)

通年手に入る乾燥のよもぎと、米を原料とした上新粉、もち米を原料としたもち粉を使用した、もっとも手軽に作れるよもぎ餅。乾燥よもぎ特有の強い風味と、上新粉ならではの歯切れよいコシのある食感が特徴です。

<材料>(作りやすい分量)
- よもぎ餅
・よもぎ(乾燥・パウダー)…7g
・上新粉…200g
・もち粉…30g
・砂糖…好みで大さじ1~2 ※入れると生地がやわらかくなる
・ぬるま湯(約50℃)…170ml
・片栗粉(または餅とり粉、きな粉)…適量 ※餅を成形するときに使用 - あんこ(粒あんまたはこし餡)…好みで適量(餅1個に対し20~30g)
- きな粉、砂糖…好みで各適量
<作り方>

1. 小さめの容器によもぎを入れ、水35ml(分量外)を加えてふやかす。
2. ボウルに上新粉、もち粉、好みで砂糖を入れて混ぜ合わせる。50℃のぬるま湯を加え、ゴムベラでざっと混ぜる。


3. 1のよもぎをもどし汁ごと加えてゴムベラで混ぜ、途中から手で揉み込み(上写真)ひとまとめにする(下写真)。

4. 8等分して小判型に丸め、真ん中をへこませ、蒸気の上がった蒸し器で15~20分ほど蒸す。

5. すり鉢、またはボウルにうつし、すりこぎでついてひとまとめて完成。食べる際は、手水をつけてちぎったり丸めたりして、お好みであんこやきな粉とともにいただく。
【よもぎ餅レシピ③】乾燥よもぎ×もち米
生のよもぎが手に入らなくても、もち生地のよもぎ餅が楽しめます。のした状態で2日ほどおけば、のし餅(切り餅)にもなります。
▼関連記事もチェック!
手作り「のし餅」の作り方はこちら>>
<材料>(作りやすい分量)
- よもぎ餅
・よもぎ(乾燥・パウダー)…7g
・もち米…2合
・片栗粉(または餅とり粉、きな粉)…適量 ※餅を成形するときに使用 - あんこ(粒あんまたはこし餡)…好みで適量(餅1個に対し20~30g)
- きな粉、砂糖…好みで各適量
<作り方>
- 小さめの容器によもぎを入れ、水35ml(分量外)を加えてふやかす。
- 「基本のよもぎ餅の作り方」の下準備と同様にもち米を浸水させ、作り方4と同様にする。
- 「基本のよもぎ餅の作り方」の作り方5のよもぎのペーストを1に置き換え(もどし汁ごと使用)、作り方6まで同様にする。
レシピ/小島喜和さん

料理・菓子研究家。季節の手仕事を得意とし、梅仕事や味噌作りなど、各種ワークショップを開催。また、ニューヨーク、パリの製菓学校で製菓、製パンを学び、ディプロマを取得した経験を活かし、料理教室、お菓子教室を主催している。
高知県出身で、地元の郷土料理や食材を広める活動はライフワーク。『心ふるえる土佐の味』(高知新聞社)、『みそさえあれば。』(日東書院本社)、『四季を愉しむ手しごと』(河出書房新社)など著書多数。
商品の取扱いについて
記事で紹介している商品は、日本橋三越本店 新館地下2階 富澤商店にてお取扱いがございます。
※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。
※オンラインストアでは商品によりギフト包装が出来ない場合がございます。詳しくは各商品ページの「ギフト包装」をご確認ください。
Ranking
人気記事ランキング