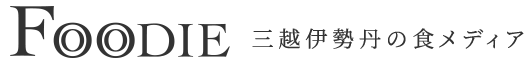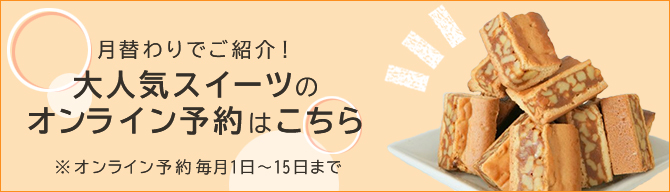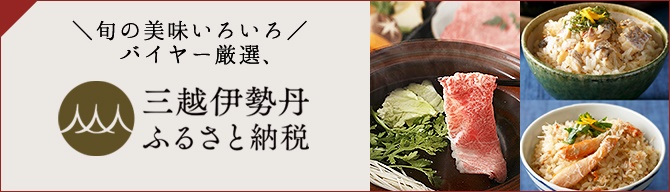2016.01.06
桜餅は東西で違う! 関東の長命寺と関西の道明寺、生地・形・葉っぱの意味を専門家が解説!

寒い冬が過ぎると、麗らかな春がやってきます。四季折々の風情を楽しむ日本では、桜前線の北上とともに日本列島が春の喜びに包まれていきます。そして、桜を愛でるばかりでなく、舌でも味わうようになったのが「桜餅」です。ところが、さまざまな文化が東西で異なるように、桜餅も東西で姿形が異なり、桜餅を包む葉にも違う特徴がみられるのをご存知でしょうか。和文化研究家の三浦康子さんに詳しく教えていただきました。
【関東の桜餅の特徴】クレープ状の形をした小麦粉を使った生地

関東の桜餅は、小麦粉を薄く焼いた生地で餡をくるんだクレープ状のスタイルです。
そもそも桜餅は江戸発祥で、江戸時代の後期に隅田川名物として広まりました。8代将軍・徳川吉宗が隅田川沿いに桜を植えさせて以降、向島の隅田堤は桜の名所として大変にぎわいました。すると、向島の長命寺の門番だった山本新六が、桜の葉で茶菓子を作れないかと思案し、塩漬にした桜の葉で包んだ桜餅を作りました。享保2年(1717年)、その桜餅を長命寺の門前で売り始めると、たちまち大評判になったのです。そんな由来からこの形と同じ桜餅を「長命寺」と呼ぶことがあります。
【関西の桜餅の特徴】まんじゅう状の形をした道明寺(どうみょうじ)の生地

関西の桜餅は、道明寺粉を蒸した生地で餡を包んだまんじゅう状で、「道明寺」と呼ばれています。
つぶつぶとした食感が特徴の道明寺粉は、もち米を蒸して乾燥させ粗挽きしたもので、大阪の道明寺で保存食として作られたのが起源です。道明寺粉を使った桜餅は比較的後の時代に登場し、明治30年(1897年)ごろに、嵯峨名物として京都で売り出したという記録が残っています。
このように、出身地によって馴染んだ桜餅が違うので、互いの存在を知ると驚く場合が多いはず。ただ、流通や情報の発達した近年は双方の垣根が低くなっており、好みで選べるようになってきました。これも時代の流れといえるでしょう。
桜餅を包む「桜の葉の塩漬け」の産地は伊豆大島が9割。東西でサイズに違いがあった!
桜餅の特徴は、なんといっても桜の葉の塩漬けでくるんであること。東西で葉の大きさに好みがあり、関東では大きめ、関西では小さめが好まれているとか。
桜餅を食べるときに、塩漬けの葉を食べるか食べないかは好みが分かれるところですが、あの香りと塩気が餅に移り、独特の風味を醸し出してくれます。桜の葉は塩漬にすることで、クマリンという芳香成分が生まれ、風味豊かになるそうです。市販の塩漬けには、やわらかくて毛が少ない大島桜の葉が使われています。その名の通り大島桜は伊豆大島付近が原産で、桜の葉の塩漬けのおよそ9割が伊豆地方で生産されています。
桜の葉の塩漬けは意外と簡単にできるので、手作りする方も少なくありません。大島桜が手に入らない場合には、八重桜などでもOK。桜の葉をさっとゆがいて冷水にとり、水気をとってから塩漬けしておけばでき上がりです。1年以上保存ができ、菓子や料理に使えてとても便利。さらに八重桜の花も塩漬しておくと、桜茶に使うなど楽しみが広がるでしょう。
桜餅は春の季語にもなっており、いろいろなところに文化が垣間見えるのでした。

三浦康子(みうらやすこ)
和文化研究家。古き良き日本の文化を今に生かす方法をTV、ラジオ、新聞、雑誌、Webなどで提案。NHK「マイあさラジオ」、フジテレビ「ノンストップ!」などレギュラーも多数。順天堂大学非常勤講師もつとめ、「行事育」提唱者としても注目されている。著書『子どもに伝えたい 春夏秋冬 和の行事を楽しむ絵本』(永岡書店)、『粋なおとなの花鳥風月』(中経出版)ほか多数。http://wa-bunka.com/
※本記事に掲載された情報は、掲載日時点のものです。商品の情報は予告なく改定、変更させていただく場合がございます。
Ranking
人気記事ランキング